はじめに
最近、「言われた通りにやらない部下」に悩む管理職の話をよく聞きます。
「なんで指示を守れないんだろう・・・」「なんでそうなるの?」とイライラすることもありますよね。
今回読んだ榎本博明さんの『「指示通り」ができない人たち』は、こうした悩みを心理学の視点で整理し、具体的な解決のヒントを示してくれる一冊です。
本の特徴
- 会話形式で進む
管理職が困りごとを相談し、著者が回答する形式なので読みやすい - 相談内容から問題点を具体化
行動の背景を整理するプロセスが見えて、「なるほど」と納得できる
部下の行動例
本書では、よくある部下の行動として次のようなパターンが紹介されています。程度の差はあれど、みなさん「あぁ~、こういう人いるよね・・・」と感じるかと(^^;
-
自己流にアレンジしてしまう
指示は理解しているのに、自分のやり方で進めて失敗する -
同じミスを繰り返す
注意しても改善されない -
やる気がなく受動的
指示を待つばかりで自発的に動かない -
感情的になりやすい
指摘や注意で不機嫌になり、指導が難しい
能力改善の3つの柱
著者は、部下の困った行動を改善するには 3つの能力の観点 で整理すると分かりやすいと説いています。
-
認知能力
-
知識・スキル・論理的思考力
-
例:手順書を理解できない、論理的説明が苦手
-
-
メタ認知能力
-
自分の理解や行動を客観的に点検・修正する力
-
例:指示を理解したつもりで進める、同じ失敗を繰り返す
-
-
非認知能力
-
感情コントロール、協調性、やり抜く力など
-
例:感情的になる、やる気がない、チームワークが苦手
-
改善の具体策(職場向け)
| 能力 | 職場での弱さの例 | 改善策 |
|---|---|---|
| 認知能力 | 指示理解ミス、手順忘れ | 手順書化、理解度確認、ロジカル思考訓練 |
| メタ認知能力 | 「分かったつもり」で進める、同じミスを繰返す | 復唱確認、日報振り返り、フィードバック受容 |
| 非認知能力 | 感情的、やる気なし、協調性欠如 | 小さな達成体験、感情コントロール、ロールプレイ |
例)先輩からのアドバイスを意地悪としか受け止めない新人
職場で「先輩からのアドバイスを意地悪としか受け止めない新人」に悩む管理職は少なくありません。これは単なる性格の問題ではなく、心理学的な原因であるメタ認知能力の不足が関係していることもあります。
この書籍からの例として、新人の誤った受け止め方の背景と、具体的な部下指導の方法をザッと整理しました。書籍でも悩める管理職と、その相談を受ける著者の会話形式で進んでいくので、読みやすくスッと理解できる内容になっています。
相談の始まり:新人の意地悪と感じる訴え
管理職Aさんの相談内容:
「新人から『先輩たちから意地悪ばかりされている』と相談がありました。しかし、職場の雰囲気は良好で、どこに問題があるのか調べるため、新人の日頃の様子や先輩たちの意見も聞きました。」
榎本先生のコメント:
「いいですね。一方的な話だけでは実態はわかりませんから、正しい対応です。」
先輩たちによると、新人は物覚えが悪く、何度も教える必要があるとのこと。
しかし新人本人は、それを「意地悪」と受け止めてしまっている様子。
問題点の整理:受け止め方の歪みとメタ認知能力の欠如
-
新人の視点:アドバイス=意地悪
-
先輩の視点:根気強く教えているだけ
-
新人の反応:「説教ですか?」「上から目線では?」と過剰に敏感
榎本先生の分析:
「熟練者が未熟者に教える場合、構図としてどうしても上から目線になってしまいます。それに過剰に反応してしまうことが問題の本質です。」
このケースでは、新人のメタ認知能力の欠如が根本原因としています。
新人は「自分のやり方が間違っていた」という事実に目を向けられず、「否定された」とだけ感じてしまっているようです。やり方が間違っていなければ、注意されることもアドバイスされることもなかったはずだ、という点に気付いてもらう必要があると分析しています。
具体的な対応策:メタ認知を育てる部下指導
で、どうするの?という点については以下3つの点について対話する必要があるとしています。
1. 仕事のやり方と自分自身を切り離す
-
「仕事のやり方」は否定されても「自分自身」が否定されたわけではないことを理解させる
-
冷静に受け止める習慣を作る
2. 指摘やアドバイスは成長の糧と理解させる
-
指摘しない方がむしろ意地悪
-
間違いを放置すると成長できないことを納得させる
3. 上から目線に過剰反応しない姿勢を育てる
-
熟練者から学ぶ姿勢が欠けると本人が損をする
-
注意やアドバイスを自己成長に活かす意識を持たせる
ポイント
-
相談 → 分析 → 問題点の特定 → 解決策の順で整理する
-
部下を単なる能力不足と決めつけず、どの力が弱いかを見極める
-
メタ認知能力の育成が、部下指導の成功につながる
まとめ:部下指導で意地悪と感じる新人への実務対応
-
部下がアドバイスを意地悪と受け止める原因はメタ認知能力の不足
-
「仕事のやり方」と「自分自身」を切り離す視点を育てる
-
指摘やアドバイスは成長の機会と理解させる
-
過剰な防衛反応を改善し、学ぶ姿勢を持たせる
💡 実務でのヒント:
部下の行動と能力を整理して改善策をセットで考え、復唱確認や小さな成功体験など日常業務に取り入れやすい工夫を活用しましょう。
こんな人にオススメ
-
新人や部下の指導に悩んでいる管理職・リーダー
-
部下指導に心理学的な根拠を取り入れたい人
-
メタ認知を育てて部下の成長を促したい人
-
職場でのコミュニケーション改善や、指示通りにできない部下への対応方法を学びたい人
💡 ポイント
困った部下に当ったとき、単なる「性格の問題」と片付けず、部下の行動の背景にある心理的要因を理解し、実務に活かすヒントを得られると思います。
【内容紹介】
●なんでそうなるの?
自分の力量に気づかず、「できる人」のようにふるまって迷惑をかける人、取引先に一緒に行っても、まったく違う理解で物事を進めてしまう人、状況の変化に対応できず、すぐにパニックになってしまう人、そもそも「指示通り」に動くことが難しい人……。そういう職場にいる人たちを紹介しながら、その改善策も一緒に考えていく本。
そういう人たちの深層心理を理解することで、改善策にも近づくことができる。様々なケースをもとに、心理学博士の著者と悩める上司の会話で文章を展開。
●周囲にこんな人はいないだろうか?
アドバイスを意地悪と受け止める/自分はできる社員と思い込んでいる/すぐにパニックになる/評価してもらえないとすぐヤケになる/「指示通り」に動くのも難しい/すぐに記憶がなくなる/意欲が空回りする など
【目次】
プロローグ
第1章 認知能力の改善が必要な人
コミュニケーション・ギャップが酷い
取引先や顧客とのトラブルが目立つ
すぐに記憶がなくなる
パニックに弱い人
定型文がないと何も言えない
「指示通り」というのが意外と難しい
話が回りくどく、何を言いたいのかわからない
理屈が通じない
第2章 メタ認知能力の改善が必要な人
意欲ばかりが空回り
アドバイスを意地悪としか受け止めない
周囲は手を焼いているのに、仕事ができるつもりでいる
同じようなミスを繰り返す
自分は仕事ができないと嘆くばかりで改善がない
職場の雰囲気が悪いからやる気になれないという
勉強はしているのだが能率が悪い
非常に主観的で判断を誤る
第3章 非認知能力の改善が必要な人
思うような成果が出ないと落ち込み、やる気をなくす
すぐ感情的になり揉め事が多い
評価してもらえないとすぐヤケになる
注意されるとすぐに反発する
コミュ力が高いと思ったが、気持ちの交流ができない
仕事そのものの能力は高いが、人と接するのが苦手
第4章 能力改善の3つの柱
改善するにはどうするか?
認知能力を鍛える
メタ認知能力を鍛える
非認知能力を鍛える

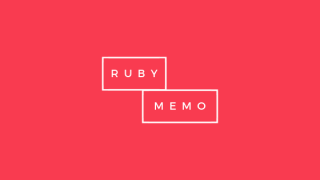
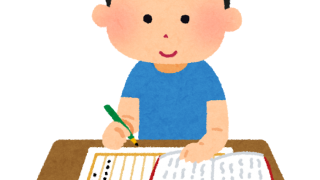





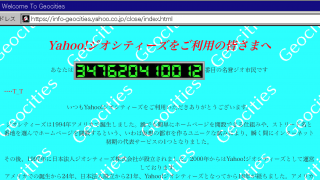

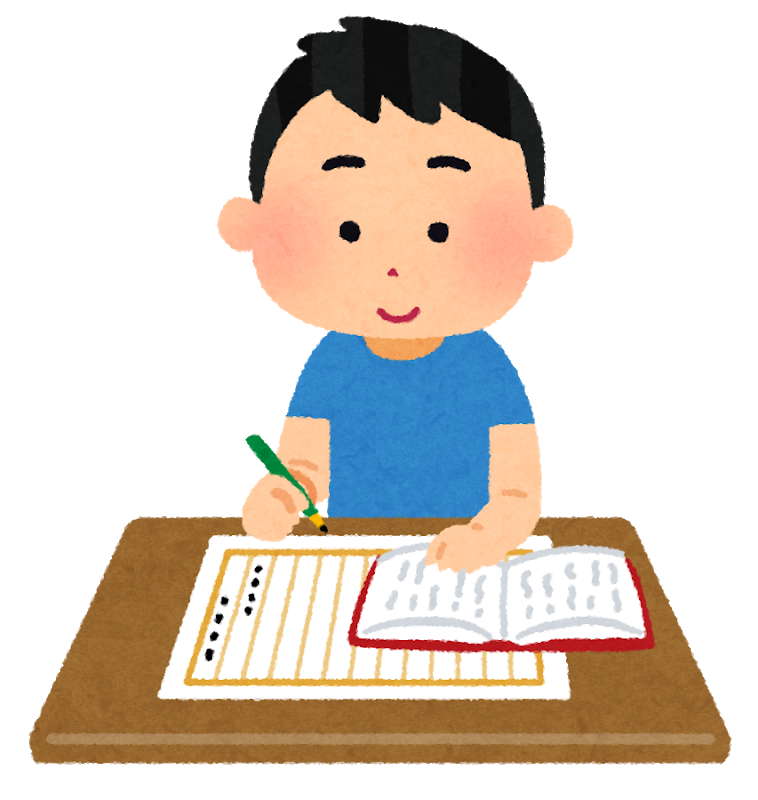

コメント